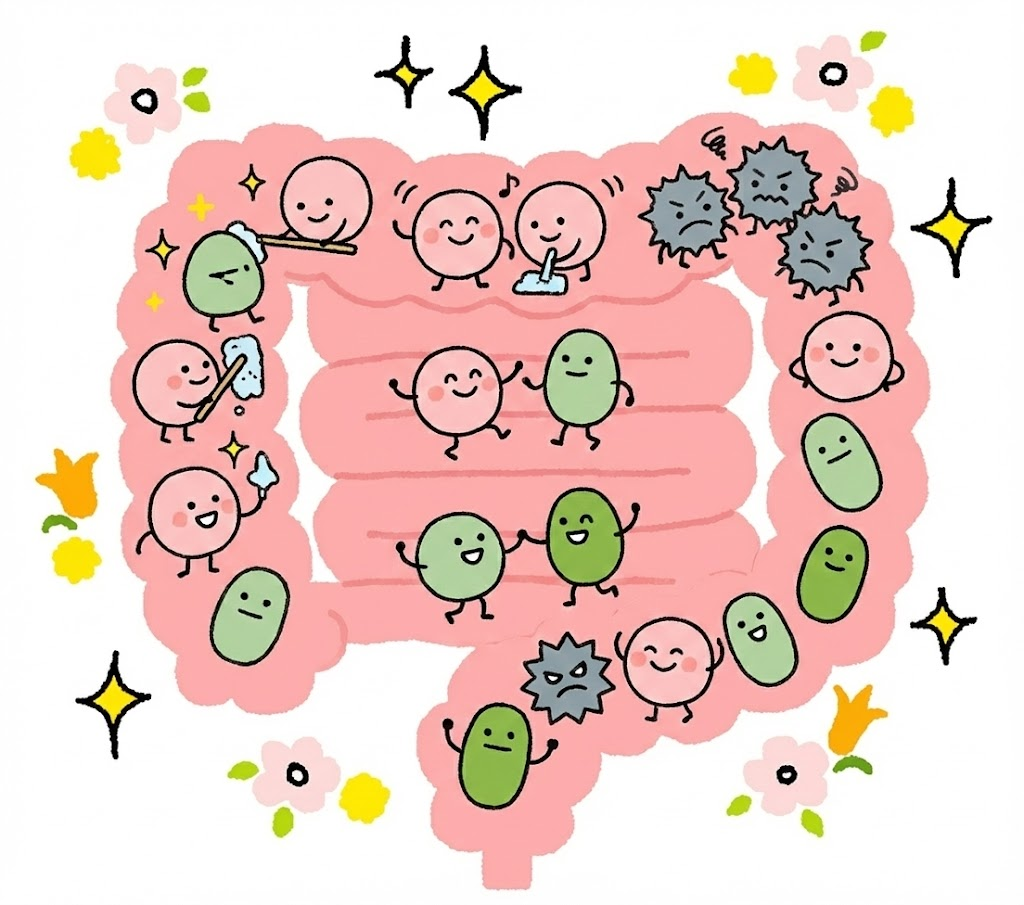
前編:腸内細菌はなぜ酸素がなくても生きられるのか
導入
最近「腸内フローラ」や「腸活」という言葉を耳にすることが増えました。 私たちの腸の中には数百兆もの微生物がすみつき、消化や免疫、さらには気分にまで関係していると言われています[1]。
しかし、意外と知られていない事実があります。 それは――腸内細菌の多くは酸素がない環境で生きているということです。
「えっ、人間の体の中なんだから、どこにでも酸素があるんじゃないの?」 そう思う方も多いかもしれません。ところが、腸の中は例外なんです。
⸻
本文
腸は、体の中でも特に酸素が少ない(もしくは全くない)環境です。 この「酸素がない状態」を嫌気(けんき)環境といいます。 一方、酸素がある環境を好気(こうき)環境と呼びます。
実は、腸の中でよく知られている大腸菌(Escherichia coli)、 ビフィズス菌(Bifidobacterium)、 乳酸菌(Lactobacillus)といった菌たちは、 「酸素がない方が元気に増える」タイプなのです。 これらは通性嫌気性菌と呼ばれ、酸素があっても生きられますが、 酸素がないほうが活発に増殖します。
腸内細菌たちは、食べ物の残りかすなどを化学反応で分解し、 新しい物質を作り出します(これを「代謝」といいます)。 この代謝によって、私たちの健康に良い影響を与える物質もあれば、 逆に病気のリスクを高めるものもあります。
例えば、漢方薬の成分は、そのままでは腸に吸収されません。 腸内の微生物がそれを分解・変換して初めて、体に吸収できる形になります。 また、腸内細菌が作り出す物質の中には、がんや生活習慣病に関わるものもあります。 それほどまでに、腸内細菌と私たちの健康は密接に結びついているのです。
⸻
結論
腸内細菌は、酸素がないという過酷な環境で、 お互いに支え合いながら、私たちの体の中で共生しています。 人間は酸素がないと生きられませんが、彼らにとってはそれが"普通の生活"なのです。
次回の後編では、 「そんな腸内細菌たちをどうやって研究するのか?」 ――その難しさと、最前線の挑戦についてお話しします。
⸻
参考文献
[1] Willem M de Vos, Patrice D Cani et al., Recent advances in basic science, 2022

